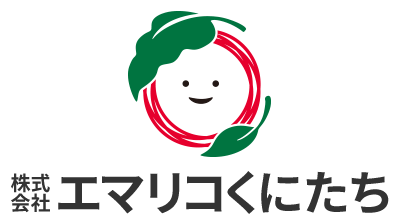拝啓、うまい!に背景あり
社長のBLOG
- TOP
- 代表 菱沼勇介 BLOG一覧
- 自給率向上とはバトルである!
自給率向上とはバトルである!
拝啓 東京農業を応援いただいている皆様
食糧自給率の向上が叫ばれて久しい。
食糧自給率について言いたいことは色々あるが、今日はひとつだけに絞って語りたい。
自給率とはバトルの結果である
ということである。
(なお、私は自給率向上に反対ではない。しかし、今回のブログでは、現在の自給率向上論に異論を唱えていく。)
カロリーベースの食料自給率の式は、
【 国産の生産カロリー / 日本人の全食料カロリー 】
である。
そのため、「そうか、じゃあ国内の生産を増やせばよいのか」という誤解が跋扈している。
おそらく、その社会的誤解を認識していても、その誤解は農業的地域への支援政策、ひいては選挙の票につながるから、あえて誤解を解こうとしない人もいるだろう。
しかし、生産を無理に増やせば価格は下がり、結果、農家が困ることになる。なぜなら人口は減っていくのだから。
いくら生産を助けたって、結局、生産は減る。
増やすべきは供給ではない。
増やすべきは、国産農産物の需要、である。
ここで、自給率という言葉をもういちど考えよう。
自給率が真に表していることはなにか?それは、
国産と外国産のシェア争いの結果
である。
めちゃめちゃ単純な話なのに、ほとんど聞くことがないのは不思議なことだ。
シェア争いの勝敗は、供給量で決まるのではなく、差別化やコスト低減で需要側にどれだけ影響を与えられたかで決まる。
すなわち、自給率向上とは、市場でのバトルなのである。
たとえば、干し芋業界は一時中国産に押されたが、見事な反転攻勢でシェアを取り返した。
小麦は日本の気候や風土にあわないとの常識が懸命の品種改良によって覆され、パスコの食パン「超熟」には国産小麦が使われるようになった。
必要なのは、ひとつひとつのマーケットで消費者や加工メーカーに国産を選んでもらうことだ。
そして、このバトルは、日本だけで行われているわけではない。日本から輸出される農産物も計算式の分子に含まれるからだ。
国内における輸入品とのバトルに加え、海外のマーケットにおける現地品や他国からの輸入品とのバトル、その結果が自給率という数字になるのである。
戦いの要諦には、先にあげた差別化もコスト低減も大事だが、さらに勢いとか流れといったものも大事である。
孫子の兵法に言う、「激水の疾くして、石を漂わすに至る者は勢なり。」
VS外国産というチャレンジングな戦いには勢いを必要とする。
そして、勢いを生むのはダイナミックな民間活力である。
ちまたの自給率向上の論点には、そういう力学的な観点がない。
(ちなみに、自給率向上を強調する論者は、”日本の農業は衰退中だ”という印象を根っこに持っているが、私は衰退しているとは考えていない。離農する人が多いこと、イコール、衰退産業ではないのである。
詳しくは、バックナンバー「だって生産性はあがっちゃうんだもの」を参照。)
他の回でも書いたが、もっとも力を入れるべきは日本酒の輸出ではないかと思っている。が、ここを説明すると長くなるのではしょりたい。
もうひとつ重要なことを。
今後、このような考え方の切り替えが絶対に必要となってくる理由がある。
人口減少という確定した未来において、とある転換点が近づいているからだ。
それは、
「自給率100%を達成したとしても、日本のすべての田畑が稼働したら食料が余ってしまう」
という転換点である。
(参考:『日本のコメ問題』小川真如著)
おそらく、自給率向上を唱える皆さんは、景観とか地域文化とか食育とか、そういう田畑が持つ多面的な機能も評価したうえで田畑を守りたいのだと思う。しかし、このままいけば、いくら自給率を高めたって田畑が余ってしまうのだ。
このことは強調してもし足りない。
であれば、やるべきことは輸出しかないのは、私にとっては自明である。にもかかわらず、細かい国内政策のことばかり議論している(それがぜんぶ不必要とは言わないが)。
輸出に向けて、どれだけのイノベーションが起こせるか?
マーケティング戦略はどうするか?
それは民間の得意分野であり、政府は裏方に回る分野だ。政府には勢いを生むサポートをしてほしい。
たとえば、キウイフルーツのゼスプリには、果物市場のシェア争いという観点でだいぶやられているわけだが、これと同じような発想の輸出マーケティングが日本政府にできるかとえいば、否だろう。
民間企業の発想にもっと頼りたい。
参考として、私が執筆した以下の記事をあげておく。
輸出目標3000億円。ドン・キホーテが仕掛ける、JAPANブランドの大攻勢!【大企業は農業を変えるか?第4回】https://agri.mynavi.jp/2022_03_18_186868/
繰り返すが、自給率の向上そのものに反対ではない。
だけど、ぶっちゃけ、人口が大幅に減っていくなかでは、自給率向上という文脈で議論している場合ではない。
これはマーケットでの戦いなのだ。必要なのは需要だ。
そして、それを生むための戦略と戦術だ。
考え方の転換が、いま求められている。
菱沼 勇介(ひしぬま ゆうすけ)
プロフィール

株式会社エマリコくにたち代表取締役。
1982年12月27日生まれ。
農地のない街・神奈川県逗子市に育つ。
一橋大在学中に、国立市にて空き店舗を活かした商店街活性化活動に携わる。2005年に一橋大商学部卒業後、三井不動産、アビーム・コンサルティングを経て、国立に戻る。NPO法人地域自給くにたちの事務局長に就任し、「まちなか農業」と出会う。2011年、株式会社エマリコくにたちを創業。一般社団法人MURA理事。東京都オリジナル品種普及対策検討会委員(2019年度〜2021年度)。