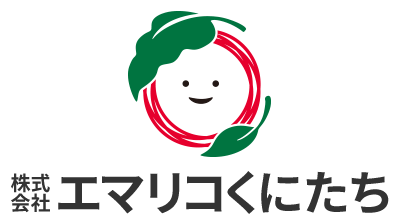拝啓、うまい!に背景あり
社長のBLOG
- TOP
- 代表 菱沼勇介 BLOG一覧
- 本源的な資源であればこそ
本源的な資源であればこそ
拝啓 東京農業を応援いただいている皆様
たとえば、無人島に何人かのグループで漂着したとします。貴方ひとりだけが食料を獲得してきたり火を起こしたりする能力があったとして、貴方はどのような行動をしますか?
なんだかそういうマンガがあった気がしますが(タイトルは思い出せない)、能力を持っている自分自身だけが得をしようとするとすごく嫌なヤツだということになります。
ところが、日本という島では、そうは思われないようです。
能力を持っている人は自分の能力の唯一の所有者となっていて、どう使おうと勝手だというのが一般的な通念のように見えます。
無人島と、日本列島とでは、なにが違うでしょうか?
才能を発揮した人にはふつうお金が支払われるので、無人島よりは経済の役に立っていると言えるかもしれないです。しかし、対価の金額は、社会的に役に立っているかどうかとは関係がないことは自明です。(実際、ノーベル賞学者が億万長者かといえばそんなことはないです。)
いずれにしろ、才能というものは、希少な資源です。これは自己所有が認められているけれども、社会の役に立てる責任がある。
それは無人島でも日本列島でも同じではないかと私は思います。
もうひとつ、人間の社会には、本源的で希少な資源があります。
それは、土地です。
土地以外の有形資産は、結局のところ、才能と労働によって作り出されたものといえるわけですが、土地だけは作り出すことができません。にもかかわらず、工場、住居、田畑、学校、道路、あらゆるものに多かれ少なかれ土地が必要です。
土地がいかに重要かつ希少な資源であるのか。
このことをもっと社会は認識しなくてはなりません。
しかして、才能と同じように、土地を保有することには責任が伴います。社会にそれを役立てる責任です。
そのことが、あまりにも無視されているように思います。
土地を私有し、自由に処分できるということは、日本社会が長い歴史のなかで培ってきた権利だということができると思います。
これは才能も同じです。江戸時代にとある藩に生まれた武士は、どのような才を持っていたとしても、その藩のために活用することを求められたでしょう。脱藩は重罪だったわけです。
あるいは家業があれば、長男はそれを継ぐものだとされた時代もあったでしょう。
それが今は自由に転職できるし、ビザがあれば海外で働くこともできます。
これは明らかによくなった点です。
しかし、自由になっても責任は残るはずですが、自由だけが意識されているのが現代社会です。
余談ですけれども、日本の高所得者への税金が高いとその人が海外に行ってしまう、という話があります。
税金逃避は才能を完全自己所有だと思っている人の典型的行動です。成功したのは才能だけではないはずなのですが。(なお、俺は努力したんだという人がいますが、努力できることも才能の一部であり、かつ育った環境に左右されると分かっています。)
余談が過ぎましたが、才能と同様に、土地というのは希少な資源です。
土地の私有制には賛成ですが、いわば、責任私有制というべきです。
たとえば、土地の使い方にある程度の規制がかかることはやむを得ないことであり、まちづくりのために規制はより強化すべきだと私は思います。
地域社会で、土地をどう活用していくかを見ていると、はっきり申し上げて、地域社会のためにどのように活用あるいは処分をしようか、と考えている人は多くありません。収支計算が書いてあるペーパーばかりを眺めています。
その意味で、まちなかの農家さん達は実に稀有な存在です。私がまちなか農家を応援する理由です。
多くの場合、土地は親から受け継いだものです。
才能であれば自分が努力で獲得したと言えなくはないですが(努力できる環境かも本来ガチャなんですが)、土地を親から受け継いだ場合、たまたまそこに生まれたという理由しかありません。
あるいは、多摩エリアでは、鉄道会社が駅前の優良な土地を持っています。
これをどのように活用するのか。所有していることは確かですが、完全に自由にしていいわけではないです。
言いかえれば、法律上自由であることと、社会的に自由であることは別の概念である、ということです。
数年前に、【街に必須な、「若者・よそ者・ばか者」ともう一人の人物】という題名のブログを書きました。もう一人の人物とは、志ある地主のことです。
地主がどのように振る舞うかによって街はまったく変わってくる、ということを主張しました。
土地が希少な資源であることは、なにも都市部に限ったことではありません。
先日、とある離島へ行く機会があったのですが、新しく移住したい人がけっこういるのに住居を見つけることが難しく、移住者が増えないのだそうです。
では、その離島には空き家がまったくないのかというと、そんなことはない。
空き家を、さまざまな事情から、他人に貸すことがないのだそうです。
しかし、冷静に考えれば、移住したい人を受け入れなければ、その街はどんどん衰退していくことは自明です。
どんな街であれ、土地を持っている人には責任があります。それが本源的に希少な資源であるからです。
ほんとうに今の活用方法でいいのだろうか?
新しく建てる建物は、中長期的に地域社会に必要とされているだろうか?
あるいはやむを得ず売却するとして、売却先は正しいだろうか?
社会のあり方に照らし合わせて自問することが必要です。
無人島に漂着するマンガでは、高い能力がありながらも勝手な振る舞いをする者は、実に醜いです。
日本列島はそういう者ばかりになっていないでしょうか?
菱沼 勇介(ひしぬま ゆうすけ)
プロフィール

株式会社エマリコくにたち代表取締役。
1982年12月27日生まれ。
農地のない街・神奈川県逗子市に育つ。
一橋大商学部在学中に、国立市にて空き店舗を活かした商店街活性化活動に携わる。卒業後、三井不動産、アビーム・コンサルティングを経て、国立に戻る。NPO法人地域自給くにたちの事務局長に就任し、「まちなか農業」と出会う。2011年、エマリコくにたちを創業。一般社団法人MURA理事。「東京農サロン」監修。東京都東京エコ農産物認証委員会委員(R7~R9)。