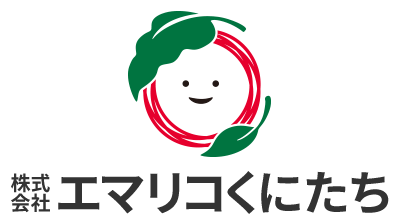拝啓、うまい!に背景あり
社長のBLOG
- TOP
- 代表 菱沼勇介 BLOG一覧
- 「変わる、変わる」というほど世のなか変わらない
「変わる、変わる」というほど世のなか変わらない
拝啓 東京農業を応援いただいている皆様
ようやくの緊急事態宣言解除となりました。
多摩エリアのみなさん、地域経済を頑張って盛り上げていきましょう!
さて、そんななか「新しい生活様式」なる意図不明なものが出てきたり、このコロナの影響で大きく世の中が変わるという雰囲気もあるようです。
すわ、ポスト・コロナの新しい時代に対応していかなくては!!
私はそうは思いません。
勘違いのないように申し添えれば、私もベンチャー企業の経営者のはしくれとして、「世の中が変化する?どんとこいや!」という気持ちは持っているつもりです。
ですが、ここで話をしたいのは、「変化してほしいか、してほしくないか」ではなく、『変化バイアス』についてです。
人間は変化を過大に認知しやすい、ということです。
前にこのブログに書いたと思うのですが、「これまでになかったスピードで世の中が動いている」という言説はけっこうマユツバだと思っています。
私も世の中が移ろうこと(たとえば東京の農地が急速に減っていること)を否定するわけではありません。社会は時代で変化する。そして経営者はそれに対応する。当然のことです。
問題は「これまでになかった」という部分です。
その根拠は何でしょうか?
たとえば日本円とドルの交換レートは、かなり安定しています。
1971年の350円から、1978年には一時200円を切り、1989年をさいごに150円以上に再浮上したことはありません。近年も、「円高だ!」「こんどは円安だ!」と叫んでいますが、こうした時期に比べれば大した変化ではない。
時代の変化スピードは人間がついていけないくらい早いものだと言われれば、それはそうかもしれません。
でも、「現代の変化が人類史上一番早い」というのはただの煽りです。
人間は変化するものに気を取られるものです。
おそらく、変化に注目することこそが、進化のなか、生き残っていくためにも大事だったでしょう。
これが『変化バイアス』が発生する一つ目の理由です。
また、何かのイベントが発生したときに、その影響を過大に見積もってしまうルートが少なくとも4つあります。
(1)リバウンドを計算に入れない:一時的な急激な変化は、そのあとある程度戻ることが多い。にもかかわらず、一時的な急激な変化を恒久的なものと考えてしまう。
(2)加速したにすぎない:イベント発生前からもともと変化している経過にあったものは、イベントによって若干加速されたとしても、結局のところ行きつくは場所は同じ。にもかかわらず、それを影響の計算に入れてしまう。
(3)変化は多くみえがち:「変化しないこと」は噂にならず、「変化すること」のみが人々の口の端に上るものである。しかして、たとえばニュースサイトやツイッターを見ると「変化する」という発信しかないので、「ああ、変化するんだな」と過大に信じてしまう。
(4)それで儲かる人々が煽る:「この時代の変化に付いていかないとヤバいですよ!」と言う(または暗にほのめかす)のが営業をする人の常套句であり、危機感をあおりたいメディアの見出しであり、新しい仕事を作りたい官僚の大義名分というものだろう。
さて、自己流に『変化バイアス』について解説した後に紹介したいのが、今話題の週刊文春のなかにあった言葉です。旬の政治スキャンダルの記事とは無関係、渋谷の著名な居酒屋「高太郎」の林高太郎氏のもの。
(以下引用)「あためて、飲食文化は人間の営みにとって大切なことなんだなと感じているところです。映画や芝居もそうですよね。文化というものは生きるエネルギーになる。いいものを観た、心の底から感動した。外食で言えば「おいしいもの食べて呑んで、また明日からがんばるぞ!」っていう。」
世の中、変わるものは変わります。
一方で、変わらないものがいくつかあることは明らかです。コロナがあったからといってテクノロジーが進化することはないし、人間の欲望が急激に変化することはないからです。
にもかかわらず、みんながみんな右向け右で過剰に反応することで、本当は必要だったものが無くなってしまう。これは本当に怖いことです。
なので、私はいわば後出しジャンケン的に、冷静に「変わるもの」「変わらないもの」「変えてはいけないもの」を見極めながら進みたいと思います。
みなさんにも、冷静な後出しジャンケンをぜひおすすめします。
菱沼 勇介(ひしぬま ゆうすけ)
プロフィール

株式会社エマリコくにたち代表取締役。
1982年12月27日生まれ。
農地のない街・神奈川県逗子市に育つ。
一橋大商学部在学中に、国立市にて空き店舗を活かした商店街活性化活動に携わる。卒業後、三井不動産、アビーム・コンサルティングを経て、国立に戻る。NPO法人地域自給くにたちの事務局長に就任し、「まちなか農業」と出会う。2011年、エマリコくにたちを創業。一般社団法人MURA理事。「東京農サロン」監修。東京都東京エコ農産物認証委員会委員(R7~R9)。