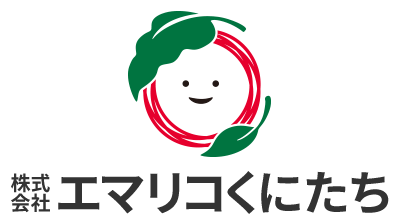拝啓、うまい!に背景あり
社長のBLOG
- TOP
- 代表 菱沼勇介 BLOG一覧
- 起業とは、そういう営みである
起業とは、そういう営みである
拝啓 東京農業を応援いただいている皆様
前回のブログで、「カフェは時代を選択する。酒場は時代を洗濯する」という、ダジャレなのか名言なのか判然としないことを書いたのだけれど(たぶんダジャレを言いたかっただけ)、とはいえ、我が社も新しい種類の商売を始めている以上は、自分たちの新しさを時代にぶつけ時代に問うていることは確かだ。
今日、国立市の谷保駅前にある「スナック水中」のメニューブックに見つけた文章を紹介したい。
ああ、この店の本質は、時代への問いなのだな、としみじみと思った。
----
これまでスナックは特定の層だけのものでした。
私たちはそんな社交場に、「多様性」の滴を垂らしたいと思っています。(中略)
先が見えない時代でも、オンラインで誰とでも繋がる時代でも、
隣人の小さな生の営みに気づき、肌で感じてもらいたい。それが私たちの願いです。
ーーーー
時代が流れ、新しい商売が生まれ、古い商売はなくなり、でも新しい商売も大半はすぐになくなる。
僕らは時代に問う。
「この新しさは必要なものではないですか?」
起業とは、そういう営みである。
もし時代に受け入れられたならば残り、じきに文化となる。
「スナック水中」という新しい業態が文化になるかどうか、注目していきたい。
かくいう我が社エマリコはどんな文化を作ろうとして、どんなことを世に問うているのだろうか?
先日、千葉商科大学の小口広仛先生が『地産地消3.0』という概念を教えてくれた。
地産地消はバブル期には概念としてスタートし(身土不二という言葉も生まれた)、それを1.0とすると、業界の人はよく知っていることだけど、00年代から大型の直売所がバンバン出てきて、スーパーには産直コーナーが設けられて、地産地消での流通量が爆発的に増えた。それが2.0時代。
しかし、小口先生は言う。
お店や商品に、生産者の名前が書いてある。たしかに顔が見えるとは言える。
でも、それだけっちゃそれだけではないですか、と。
農業がこれからも機能していくためには、消費者と生産者とのつながりが必要で、その窓口として消費地に近い農業はある。しかし、物理的に近場で流通しているだけでは、つながりを生んでいるとは言い難いわけである。
僕らの店頭でもPOPに生産者名を書いているけれど、それだけで満足してはいけないのだ。
地元の旬を楽しむという生活。
そうだ、それを時代に問うているのが「しゅんかしゅんか」という業態だった!
小口先生のお話を聞いて、初心を思い出すことができた。
今日もお昼に、かなりの炎天下だったけど、国分寺の中村清治さんの畑でジャガイモの収穫体験を行った。
大人の食農体験「イートローカル探検隊」も運営しているし、「地域循環農園 やっほー!」も保有しているし、ポッドキャスト「しゅんかしゅんかの旬ラジオ」もある。
お店ではさらに立会い販売を増やしたいと思っている。
一方で、このブログで書いてきたように、デジタル化していく時代は、消費行動もデジタルに誘う。
インターネットでポチっとすれば買い物は済む。ともすれば、AI付きの冷蔵庫が勝手に発注することもあるかもしれない。
その意味で、接客ベースで生産者のぬくもりを大事にしようという僕たちの業態は、新しいけど古いとも言えるわけである。
時代は変わっていくけれど、そのアナログな部分、街とつながるということ、あるいは季節を感じるということ、さて、それは人間の本質ではないんでしょうか?
それを時代に問う。
それを正解にするために今日も戦う。
起業とは、そういう営みである。
菱沼 勇介(ひしぬま ゆうすけ)
プロフィール

株式会社エマリコくにたち代表取締役。
1982年12月27日生まれ。
農地のない街・神奈川県逗子市に育つ。
一橋大商学部在学中に、国立市にて空き店舗を活かした商店街活性化活動に携わる。卒業後、三井不動産、アビーム・コンサルティングを経て、国立に戻る。NPO法人地域自給くにたちの事務局長に就任し、「まちなか農業」と出会う。2011年、エマリコくにたちを創業。一般社団法人MURA理事。「東京農サロン」監修。東京都東京エコ農産物認証委員会委員(R7~R9)。