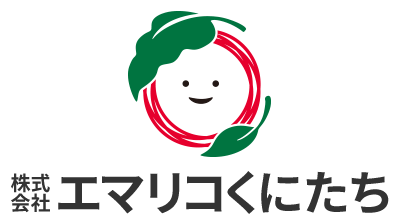拝啓、うまい!に背景あり
社長のBLOG
- TOP
- 代表 菱沼勇介 BLOG一覧
- 流通事業者にも五分の魂(悪玉論を葬りたい)
流通事業者にも五分の魂(悪玉論を葬りたい)
拝啓 東京農業を応援いただいている皆様
ちょっとネガティブな話をします。
コロナ禍での政府の言動に、私がひじょうに怒っていたことを知っている人も多いかなと思いますが、さいきん、それに似た怒りがあって。
どうもコメの高値について、中間流通業者やJAを悪玉にしようという流れを政府が作ろうとしている。少なくとも止めようとしない。
これにすごく怒っているわけです。
(選挙前に書かない方がいいかなと思って、ブログにするのがワンテンポ遅くなりました。)
当社は野菜は卸売もやっていますけど、コメは小売しかしていないので、批判されているコメの中間流通事業者にはあたりません。でも、近接業界として、黙っていられない。
JA悪玉論も反論しておきたいのですが、長くなるので、中間流通業者について書きます。
くだんの国会での発言、つまり利益の伸び率をもって「卸売業者が利益を上げ過ぎている」という発言はもうどうしようもない与太話なんですが、信じてしまう人もいると思うので解説しておきたいと思います。(会計に詳しい人は★まで読み飛ばしてください。)
一般に、もとが低い営業利益というものは、会社には固定的な費用がありますから、販売単価が少し上がると一気に上がるものです。
発言の念頭に置かれたのは木徳神糧というコメの大手卸の会社と言われていますが、5月8日に発表された決算短信(第1四半期)において、営業利益が3.4倍に増えたいうことです。
ですが、前年同期の営業利益は4.1億円で、売上高営業利益率にして1.4%しかありません。それが3.4倍になって、5.0%になった、そういう話なのです。(営業利益は金利や法人税控除前の数字です。)
しかもこの会社は多角化しているので、じつは、利益の約半分はコメ以外で稼いでいます。
前期の1.4%というのは、金利が少し上がったらあっという間に吹っ飛ぶくらいの水準です。
木徳神糧の社員は370名ほどいるそうです。このインフレ下で、営業利益率が1.4%しかなかったら、その社員の生活はどうなるのでしょうか。
これを暴利と呼ぶのであれば、いつ儲ければいいのか?
そういう想像力が政府には欠けています。
もっと言えば、過去5年のあいだに営業利益がマイナスの年もありました。営業利益が高いのが暴利という論理でいくと、マイナスで売っていたときは安く消費者に提供していたのですから、逆に褒められてしかるべきということになるはずです。当然ながら、褒められたことはないでしょう。★
なんとなれば、コメの卸業や当社のような野菜小売業を含む食品流通業界は農水省の管轄です。
具体的支援をしろとは言いませんが、その産業とその従業員を見守っていく責任はあるわけです。そのつもりがないのであれば、経産省に管轄を移していただきたい。真面目に、そう思っています。
もうちょっと付け加えると、どうもコメの流通をよりシンプルにした方が、コメが安くなるという理論があるみたいで、じつに不思議です。5次まで卸業者がいるからコメが高い、みたいな。
まあ、経済を分かっていない人の発言です。
楽天市場や食べチョクを開いてみなさいな。
直接売っている農家がたくさんいるでしょう。すでに直接買える。すでに超絶シンプルです。
JAが集荷しているコメは全生産量の30%くらいと言われています。それ以外はふつうの民間流通や縁故米なわけです。
そういう自由な市場のなかで5次まで卸業者がいるのであれば、なにかしら理由があるからです。
でもって、大手スーパーが5次卸から買っているわけがないわけで。いま大手スーパーのコメが高くてそれが問題になっているわけですから、流通の多次構造が高値の理由ではないことは、ちょっと考えれば明白です。
まあ、この流通過程をシンプルにした方がいいという言説は、いつか来た道、という気がします。
私が商学部の大学生だった頃、経済誌などでは「商社不要論」が唱えられていました。
でも、数十年経ってみてどうでしょう。
大手コンビニなんて、みんなどこかしらの商社と手を組んでいます。
あれれ、小売と生産が直接つながって商社はいらなかったはずでは?という感じです。
今回の状況では、中間流通事業者が買い占めをしているという根拠不明な、しかし広く信じられた言説もありました。
けれども、コメの市場は、買い占めをして誰かが価格操作できるような寡占市場ではまったくありません。
相場をコントロールできないのに貯めておいて後で出そうというのは、ただのギャンブル(投機)です。
ギャンブルは上場している大手企業にはできませんし、中小にしてみれば、大量のコメを捌くには、設備としての精米能力・包装能力、輸送能力(コメはかさばりますし、空前のドライバー不足です)、そしてそれなり販売先が必要ですから、全体の流通量に影響を与えるほどのギャンブルなんて非現実的なのです。
だいたい、流通過程のどこかで精米が必要で、精米したコメの賞味期限は意外に短いという、業界に1週間もいれば分かる事実を無視している論説が多すぎます。
大手卸が貯めておくとしたら、次の新米の時期まで在庫を切らさないためでしょう。在庫が切れて困るのは国民ですから(バンバン輸入していいなら話は別ですが)、おそるおそる市場に出すのが公益にかなっているというものです。
最後に、木徳神糧が利益の半分をコメ以外で稼いでいるとさきほど書きましたが、多角化している理由について推察します。いや、そのワケは明らかでしょう。
コメの需要が落ち続けてきたからです。需要が落ちているマーケットで死を待つ上場会社はありません。ほかで稼ごうとしてきたのです。
なお、最大手の神明ホールディングスも同様に多角化しています。
需要が落ちてくれば、年々、利益率は低くなっていきます。でもずっと、多角化しつつも業界に留まっていて、コメを安定的に供給し続けてきたわけです。そういうなかで、今年度、ちょっと利益額が上がった。それを暴利と言われたらあまりに酷いでしょう?
SNSでよく見かけた発言が、「高値でも農家さんの収入が増える分にはいいんだけどね」。
僕たちの営業利益率が5%あったら、それはいけないことですか?恐縮した方がいいでしょうか?
農家さんが情熱と工夫を持って食べ物を作っていることは崇高なことであり、賞賛されます。私自身もものすごくリスペクトしています。
でも、それと同じレベルとは言いませんが、私たち流通事業者も、ある程度は、情熱と工夫とを注いでこの仕事をやっているのです。
簡単に、流通のせいでコメが高値になっている、なんて言わないでほしいのです。まして所管の官庁が言うなんて論外です。
流通事業者は黒子です。黒子で構わないですし、そのことをむしろ誇りに思ってます。でも、黒子にならどんな批判をしていいわけではないのです。
当社は野菜と果物中心なので、コメ卸の会社さんとはあまり親しくないです。
でも、きっと、きっと、悲しい思いをしているのではないかと思います。そこには、この国にとって大事な食べ物であるコメを、より美味しく、より安定して、消費者や飲食店に届けていこうというプライドがある絶対にはずです。
反論するとかえって火に油を注ぐから、静かにしているんじゃないかと思います。
流通事業者も、自分の仕事にプライドを持っている。
黒子で構わないんだけれども、それだけは、市民の皆さんに理解していただきたいところと思います。
菱沼 勇介(ひしぬま ゆうすけ)
プロフィール

株式会社エマリコくにたち代表取締役。
1982年12月27日生まれ。
農地のない街・神奈川県逗子市に育つ。
一橋大商学部在学中に、国立市にて空き店舗を活かした商店街活性化活動に携わる。卒業後、三井不動産、アビーム・コンサルティングを経て、国立に戻る。NPO法人地域自給くにたちの事務局長に就任し、「まちなか農業」と出会う。2011年、エマリコくにたちを創業。一般社団法人MURA理事。「東京農サロン」監修。東京都東京エコ農産物認証委員会委員(R7~R9)。