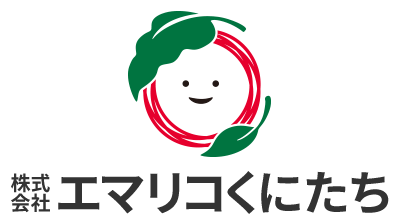拝啓、うまい!に背景あり
社長のBLOG
- TOP
- 代表 菱沼勇介 BLOG一覧
- 学校給食のレシピには感動が足りない
学校給食のレシピには感動が足りない
拝啓 東京農業を応援いただいている皆様
突然ですが、皆さんは幼少期に、どんな農業や食に関する体験をしましたか?
東京にはどんどん人が流入してきて、かなり前から世界一の大都市なわけですけれど、ここで生まれ育った子どもたちは農業や食に触れることが少ないことが想像できます。
先日、東京農サロン・歳末スペシャルに株式会社シフラの竹熊俊哉社長をお招きしました。
イトーヨーカドーの店頭に行ってみてもらいたいのですが、そこでは「顔が見える野菜。」というシリーズがかなり広範に展開されていて、市場ものと並んでパッケージに農家の似顔絵が描いてある野菜が並んでいます。スーパーで生産者名がこれほど幅広い品目で記載してあることは稀だと思います。
このブランドを展開しているのが株式会社シフラです。
竹熊社長いわく、「農家の顔が見えることに好感を持ってくれる人たちは、若いときに農に関する原体験がある人たちだ」と言っていました。
逆にいえば、農に関する原体験がなかったとすれれば、どんな商品も同じように見える、安い方がいいとだけ考えるということでしょう。
私たちが日本の農業を支えようと頑張っても、原体験の減少は、ジワジワとボディブローのように効いてくるかもしれません。
ときに、学校給食はその原体験のために重要な場だといえるでしょう。
私は、以前、マイナビ農業の記事において、地産地消に数値目標を設定するよりも以下の点が大事だと指摘しました。
『教育の現場で、「○○産のほうれん草です」とたとえば給食の献立表に書いてあったとして、どれだけの子どもの心に残るだろうかと思います。子どもは好奇心旺盛ですが、インパクトのないことはすぐに忘れてしまいます。
そう、インパクト。人の記憶に残るにはこれが大事です。』
教育とは感動ありき、だと私は思います。
まあ、感動を数値で表せるのであれば、そういう数値目標はあってもいいと思いますけれど。
最近は、オーガニック給食というのが始まっていまして、農政として推進しているようです。
しかし、オーガニックは感動や原体験となんの関係もないわけです。
まあ、むかしは、有機というのは、生産と消費の有機的つながりを指していたわけですが、いまはJAS有機、言いかえればビジネス有機です。ビジネス有機が悪いわけではないです。それは企業戦略としてはぜんぜんあり、です。
ただ、それを教育の場に持ち込むのは、率直に言って筋悪です。
現状の一般論として、栄養士さんは色々な食の感動を伝えようと頑張っているけれども、予算や人員の関係でそれが十分にできていないことが多いです。
だいたいの自治体は、多かれ少なかれ地産地消を推進しているので、農家さんと話をする機会のある栄養士さんも多いわけです。そういうところで感じた感動を、子どもたちにも伝えたいと思うこともあるでしょう。
そういうところから食育は始まるのではないでしょうか?
でも予算も時間もなかったりするわけですね。
オーガニックだからといって、何か感動が生まれるわけではないです。
テレビ報道で、オーガニック給食を食べた子どもが「やさいがおいしいです」と言っているのを流しているのを見たことがありますが、私に言わせれば、「地元の野菜の方がぜったいにうまいし安いから」。
よほどの都心でなければ地元農家の子どもも同じ学校に通っているわけですが、その子もいるクラスでオーガニック野菜が安全でおいしいんだよと教えるのでしょうか?
給食の分野において、オーガニックよりももっと予算と人手をかけるべきところがあるのは自明に思えます。
地域のなかで議論をし、結果として、オーガニックの給食をやりましょうとなるならなんら反対することはありません。
しかし、いまは、お上からの要請やなんとなくの時代の流れでそうなっているにすぎません。
たくさんの大人が動けば、やがてはそれは利権になります。
利権になってしまえばワクワクしません。
これは社会一般の定理です。
(まったく同様の理由で、給食の地産地消農産物が利権化している場合もあると推察します。すると、だんだんと子どもたちの感動が二の次になることが危惧されます。)
ま、オーガニック給食に関しては、現状は利権というところまではいってないと思いますが、ミーハーな動きだと断じておきたいと思います。
とにもかくにも、私が言いたいことはこれです。
ワクワクする学校給食を。授業ではインパクトある農体験を。
そのための予算や仕組みを真剣に考えるのが大人の責務です。
いや、仕組みなんて複雑なことを考えなくても、現場の志ある栄養士と教師に予算と裁量を渡すだけで進むことがいっぱいあると思っています。
菱沼 勇介(ひしぬま ゆうすけ)
プロフィール

株式会社エマリコくにたち代表取締役。
1982年12月27日生まれ。
農地のない街・神奈川県逗子市に育つ。
一橋大在学中に、国立市にて空き店舗を活かした商店街活性化活動に携わる。2005年に一橋大商学部卒業後、三井不動産、アビーム・コンサルティングを経て、国立に戻る。NPO法人地域自給くにたちの事務局長に就任し、「まちなか農業」と出会う。2011年、株式会社エマリコくにたちを創業。一般社団法人MURA理事。東京都オリジナル品種普及対策検討会委員(2019年度〜2021年度)。