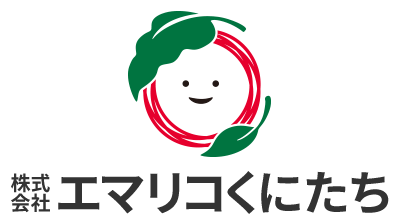拝啓、うまい!に背景あり
社長のBLOG
- TOP
- 代表 菱沼勇介 BLOG一覧
- 自治体の計画は戦略とは異なる
自治体の計画は戦略とは異なる
拝啓 東京農業を応援いただいている皆様
行政の計画と、民間企業の戦略はどう違うか?
質問を変えれば、行政の計画を戦略と呼んではいけないのか?
少なくとも、地域の農業振興や地産地消の分野では、戦略とは言えないことが多いと感じています。
地域で色々な人の意見を聞いてまとめた計画というものは総花的になりがちです。
地域が抱えている課題というのは数限りなくあります。課題を聞き取り、それに対してひとつひとつ対策を考えていく、というステップを踏むと、総花的にならない方がおかしいわけです。
しかし、よほど余裕のある自治体であれば別ですが、現代においてリソースが豊富な自治体は多くありません。リソースの裏付けがない計画など、あってもなくても同じです。
リソースというのは、予算(カネ)もそうですけど、どちらかといえばヒトです。施策ひとつひとつについて責任をもって進めていく組織や人員が確保されなければ、進みようがありません。
農業振興や地産地消の計画をスタートするときに、当該部署の人員を大幅に増やすことを計画することは稀です。
私は埼玉県S市の農業振興計画の策定に携わったときに、人員などのリソースの裏付けも計画に書き加えるべきと助言しました。実現はしませんでしたが。
民間の企業の場合、当然のことですが、何かしらの計画をスタートさせるときに人的リソースについて想定をしないなんてことはありえないわけです。しかし、それが行政ではまかり通るのです。
これは、計画を進めていく具体的なステップの検討をしていない、と言うこともできます。
具体的なステップを検討したらおのずと足りないものが見えてきて、とてもじゃないが現状のままでは実現できないな、と分かるはずです。
ここで戦略の要件ですが、目指す姿・ビジョンは当然にあるとして、さらに以下の要件が必要です。
①必要なリソースを確保する想定がある
②「選択と集中」(メリハリ)がある
③時間的な想定がある
①の必要なリソースを検討したとき、余裕のある自治体でなければ、おのずと選択と集中が必要になるはずなのです。でもそれだと課題を1つか2つしか解決できないことになってしまうから、まずこれをやって、3年後にこれをやる、という時間的な想定も出てきます。
こんなことは民間企業の社長であれば、自然とやっていることです。
つまり、『何も捨てることができない人には、何も変えることはできないだろう』(進撃の巨人) 。
こういう戦略とは呼べない計画になってしまうのは、ブレスト的な議論をして、そのあと衝突をおそれてそぎ落とす作業をしないからかもしれません。そして、なんとなく進んでいく。
もちろん多様な人の意見を聞くことは大事です。一方で、リーダーシップをとる人がいなければ、適切なリソース配分はなされません。
本当に計画を意味のあるものにするには、リソース配分をするリーダーが必要なのです。
菱沼 勇介(ひしぬま ゆうすけ)
プロフィール

株式会社エマリコくにたち代表取締役。
1982年12月27日生まれ。
農地のない街・神奈川県逗子市に育つ。
一橋大商学部在学中に、国立市にて空き店舗を活かした商店街活性化活動に携わる。卒業後、三井不動産、アビーム・コンサルティングを経て、国立に戻る。NPO法人地域自給くにたちの事務局長に就任し、「まちなか農業」と出会う。2011年、エマリコくにたちを創業。一般社団法人MURA理事。「東京農サロン」監修。東京都東京エコ農産物認証委員会委員(R7~R9)。